2021.10.08
出産

皆さんは「切迫早産」という言葉をご存知でしょうか。現在妊娠をされている方は、切迫早産について、病院から指導があった方もいるのではないでしょうか。また似たような言葉に「早産」がありますが、言葉の意味に違いはあるのでしょうか。今回はそんな切迫早産・早産についてのお話です。切迫早産の原因や症状、治療方法や日常生活の注意点ついてご紹介しますので、参考になりましたら幸いです。
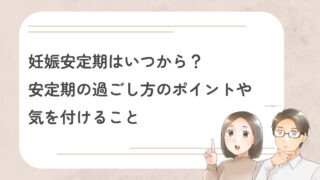
まずはじめに切迫早産についてご説明します。切迫早産とは、妊娠22週以降37週未満の時期に、早産が切迫した状態、すなわち早産に至る可能性が高い状態のことを言います。
一方早産とは、22週以降37週未満の出産自体のことを呼びます。早産の場合は、出産となった週数や赤ちゃんの大きさによって、医療処置を必要とするため、なるべく早産を避けるようにする必要があります。
切迫早産と早産の違いについてまとめると、
妊娠22週以降37週未満で、まだ生まれていないけど生まれそう(早産が切迫した状態)が切迫早産で、22週以降37週未満の出産(生まれた)が早産です。
その他、出産の区分になります。
流産:妊娠22週未満の妊娠の中断
早産(早期産):妊娠22週から37週未満の出産
正期産:分娩予定日を含む妊娠37週から41週6日までの出産
過期産:42週以降の出産
※分娩予定日は、最終月経の初日に280日を足した日として計算しています。
早産をなるべく避ける理由として、早産では赤ちゃんの発育が不十分なことから、低出生体重児になることが多いとされています。
低出生体重児は、体重あたりの体表面積が大きくなることから、体温を保つのが難しく、低体温に陥りやすいとされています。また通常の赤ちゃんと比べて体力の消耗が激しくなり、低血糖、貧血、黄疸のリスクが挙げられます。
その他低出生体重児のリスクとして、呼吸障害があります。
わたしたち人間は肺で呼吸を行いますが、肺は一番最後に作られる器官であり、だいたい妊娠34週頃に完成すると言われています。それより早く産まれた場合は、呼吸窮迫症候群(RDS)などの呼吸障害を起こしやすい可能性があり、より手厚いケアが必要となります。
出産後について、赤ちゃんの産まれた週数や状態によっては、NICU(新生児集中治療室)などで治療しながら成長を促します。赤ちゃんの大きさによっては、NICU に入らないで経過を見ることもあります。

切迫早産の原因はさまざまなものがあります。主な原因は以下です。
切迫早産の原因で最も多いのが子宮内感染です。子宮内感染の中でも、頻度が高いのが「絨毛膜羊膜炎」で、膣内にいる善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れることによって起こります。
赤ちゃん包む膜に炎症を起こすと、炎症物質の作用により、膜が破れやすくなったり、子宮収縮が促進されたりするため、切迫早産の原因になります。
「子宮頸管無力症」は、出産前に子宮の入り口が開いてしまうことを言います。出産時に子宮の入り口は開きますが、それまでは妊娠の継続のためにしっかり閉じていなければなりません。
子宮頸管無力症を引き起こす原因は分かっていませんが、もともと子宮頸管の組織が弱い場合や、子宮頸がんの手術経験がある場合はリスクになります。
羊水過多は、子宮内での羊水の産生が増えたり、吸収が減ったりすることによって起こります。羊水はお腹の赤ちゃんを保護するためにありますが、赤ちゃんの消化器に異常があると、羊水が一定量よりも増えるようになります。
羊水は増えすぎると子宮内の容量が増えるため、お腹が張りやすくなり、切迫早産の原因になります。
子宮筋腫は子宮の筋肉由来のできもの(良性腫瘍)です。本人の自覚症状がなく、妊娠をきっかけに子宮筋腫が見つかることもあります。子宮筋腫より子宮内の血行が悪くなると、筋腫の壊死が起こり、早産の原因になることがあります。
なお、妊娠中に子宮筋腫が見つかった場合は、保存的な治療を行います。
生まれつき子宮の形が正常とは異なることを「子宮奇形」といいます。子宮に奇形があると、妊娠しにくかったり、妊娠しても赤ちゃんが育ちにくかったりすることが分かっています。
子宮奇形にはいくつかのタイプがありますが、早産を起こしやすいものもあります。
双子や三つ子などの多胎妊娠は、通常の妊娠よりも子宮が大きくなるため、子宮収縮が起こりやすくなります。多胎妊娠の場合は、妊娠20週と28週あたりに、経腟エコー検査により、子宮の入り口部分である「子宮頸管長」を計測します。
子宮頸管長が短くなると、早産のリスクが高まることが分かっています。子宮頸管長が短くなっている場合は、切迫早産の予防のために入院治療を行います。
近年、歯周病が全身病を悪化させる事実が注目されています。歯周病により、炎症物質である「サイトカイン」が血液中に増えると、子宮筋が収縮して切迫早産のリスクが高くなります。
喫煙は切迫早産のリスク要因です。タバコに含まれるニコチンは、血管を収縮させる作用があります。妊婦さん本人の喫煙だけでなく、家族内や受動喫煙も切迫早産のリスクを高めるので注意が必要です。

続いて治療方法についてご説明します。場合によっては赤ちゃんが子宮内で生きられない状態になり、人工的に早産にせざる得ないこともあります。早産、すなわち予定よりも早く出産してしまった場合は、出産となった週数や赤ちゃんの大きさによって、医療処置を必要とします。ゆえに切迫早産の場合は、早産にならないための治療を行います。
切迫早産の治療の目的は、子宮収縮を起こさないよう、安静にすることです。正期産である37週未満に陣痛や前期破水など、お産の兆候が見られたら必要時入院をします。入院中は安静を保つことや子宮収縮抑制薬を継続的に投与することにより、できるだけ妊娠期間を延長させ、正期産での出産を目指します。感染兆候が見られる場合には、抗菌薬を投与し、治療を行います。

切迫早産の治療法の一つとして、入院はせずに、自宅で安静にして経過を見る場合があります。 また、入院が必要でも、上のお子さんがいる、周囲の協力を得ることが難しいことから、入院はせずに自宅での安静を行うことがあります。
切迫早産の場合、赤ちゃんはお腹に止まっている状態なので、できるだけ妊娠を継続できるよう、自宅療養の場合でも、安静が第一です。状態によっては長期安静の指示があることもあります。気持ちをリラックスさせて、食事や睡眠が十分取れるよう、環境を整えましょう
自宅療養における日常生活の注意点として、なるべく子宮収縮が起こらないようにすることが大切です。自分一人の体ではないことを自覚し、大切にいたわりましょう。
程度にもよりますが、なるべく横になる時間を長くするよう指示がある場合があります。「これくらいは大丈夫かな」と無理をするのではなく、医師の指示を守り、安静を保ちましょう。入浴はシャワー浴ではなく清拭(ベッドの上で濡れタオルで体を拭くなど)の指示がでることもあります。
安静にしていると、運動不足から便秘になりやすくなることがあります。便秘になると子宮が圧迫されたり、トイレでいきんだりすることによって子宮収縮を起こしかねません。便秘については妊娠中でも使えるお薬があります。主治医の先生に相談しながら排便のコントロールと治療を行いましょう。
仕事への配慮について、職場に配慮してほしいと伝えにくい時は、「母性健康管理指導事項連絡カード」の使用をお勧めします。働く妊婦や産後の女性の健康状態を守るために、医師から指示事項(通勤緩和や休憩について)を職場に正しく伝えるために利用できる書類です。特に切迫早産の場合、仕事内容や休憩について、綿密な配慮が必要な場合や、仕事自体が難しい場合もありますので、こちらのカードを使用し、仕事内容の調整を行うことをおすすめします。
日本では、生まれた赤ちゃんの5~6%が、在胎37週未満で生まれています。早産で生まれた赤ちゃんは、NICU(新生児集中治療室)に入院となり、呼吸や栄養の医療管理が必要になります。
早産で生まれた場合、在胎週数が短いほど、赤ちゃんの生存率は低下する傾向があります。その一方で、新生児医療の進展により、妊娠28週未満で生まれた超早産の赤ちゃんの生存率は向上しており、全体の生存率は92.3%となっています。
在胎週数別のNICUにおける早産で生まれた赤ちゃんの生存率は以下になります。
上記からも、早産の赤ちゃんの生存率が高いことが分かります。一方で、NICUで医療管理を受けていても、肺炎や敗血症などで亡くなる赤ちゃんもいます。
また、早産で生まれた赤ちゃんは、退院後も呼吸器の感染症が重症化しやすいことが分かっています。正期産で生まれた場合も、2歳未満の乳幼児でも肺炎や気管支炎で入院することがありますが、超早産で生まれた赤ちゃんは、再入院の確率が高いといわれています。
早産で生まれた子どもが感染症にかかりやすいというわけではありませんが、健康状態によっては重症化しやすくなります。退院後も、赤ちゃんの様子をよく観察して、異変がみられる場合は、早めにかかりつけの小児科医へ受診させましょう。
妊婦さんが切迫早産を防ぐには、健康的な妊娠生活を送り、体に無理をしないことが大切です。妊婦健診は妊娠週数に合わせて定期的に通い、自分や赤ちゃんの健康状態の確認を受けましょう。
切迫早産を起こしかけている場合は、医師の指示に従い、適切な治療を受けましょう。以下のポイントは、切迫早産のリスク低下につながります。
セックスをするときは、コンドームを使うようにしましょう。妊娠中は経過に問題がなければ、パートナーとのセックスすることが可能です。コンドームを使用せずにセックスをすると、子宮内の感染を引き起こす可能性があります。
とはいえ、妊娠すると女性の性欲が低下したり、体位が辛くなったり感じることもあります。普段通りにセックスをするのが難しい場合は、スキンシップをするなどお互いが満足できるように努めましょう。
妊娠期間と歯茎の状態には相関関係があります。歯周病は切迫早産のリスクを高めるので、出産前にきちんと治療を受けることが大切です。妊娠中の歯科治療は、基本的にいつでも受けられますが、大事を取るなら、つわりの終わった安定期から臨月前までが適しています。
また、歯周病がなくても、歯石除去をすることで、血液中のサイトカインを減らすことにも役立ちます。
妊婦さんの切迫早産を予防するために、家族全員で禁煙に取り組みましょう。喫煙の欲求は、脳のドーパミンが関係しているため、気力だけで禁煙するのは難しいものです。禁煙を成功させるために、医療機関の禁煙外来で治療薬を用いながら取り組むこともできます。
また、家族内で喫煙者がいなくても、受動喫煙に注意するようにしましょう。
疲労が蓄積して心身にストレスがたまると、感染に対する免疫力も低下したり、お腹が張りやすくなったりします。切迫早産の予防のためにも、睡眠や休息を十分に取って、体の抵抗力をつけましょう。
特に、妊娠中は心身の変化により、普段よりも疲れやすさを感じる方も多いです。妊娠している間は、あまり無理をしすぎないようにすることが大切です。
切迫早産のリスク要因はいくつかあるので、自分で気を付けていても起きてしまうことがあります。切迫早産になりやすい人は以下になります。
切迫早産は、ストレス管理や喫煙など生活習慣と関わっているものもあれば、生まれつきの子宮奇形など、対策が取りづらいものもあります。もともと切迫早産のリスクが高い人は、定期的に妊婦健診を受けて、妊娠管理を行っていきましょう。
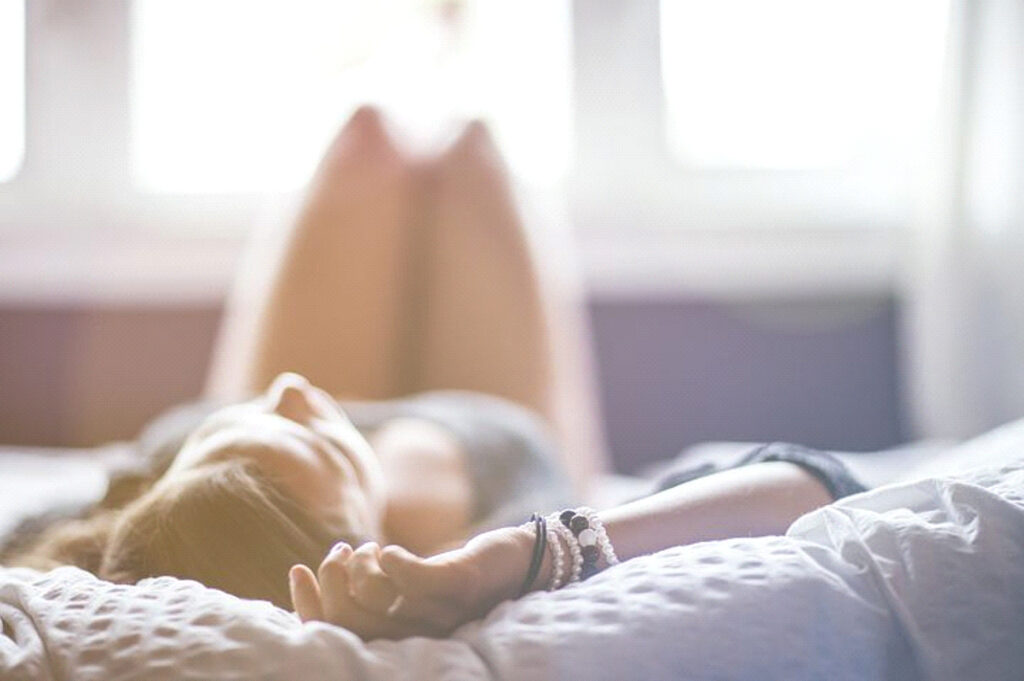
今回の記事では、切迫早産について、早産との違いや原因と症状、治療方法や日常生活における具体的な注意点についてご紹介しました。
切迫早産とは、妊娠22週以降37週未満の時期に、早産に至る可能性が高い状態のことで、なるべく早産を避けるようにする必要があります。
感染症をはじめとした様々な原因があり、症状として、いつもと違う、規則的なお腹の張りや痛み、出血、悪臭のあるおりものや水っぽいおりもの(前期破水)が継続的に出ます。
子宮収縮を起こさないよう、安静や投薬でできるだけ妊娠期間を延長させ、出産となります。自宅安静の場合は、なるべくリラックスできる環境を整えることが大切です。
切迫早産は、場合によっては長期安静の指示があることもあります。リスクがあることを自覚し、リラックスできる環境を整え、ご自身の体をいたわりながら妊娠期間を過ごしていただければ幸いです。
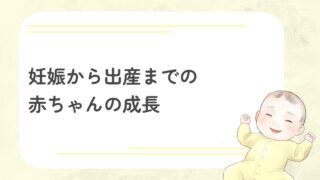
ABOUT ME