2021.06.07
出生前診断

クラインフェルター症候群という、男性の性染色体にX染色体が一つ以上多いことで生じる疾患に関して、具体的なメカニズム・症状・関連する合併症・治療などについて詳しく説明していきます。

クラインフェルター症候群とは、性染色体の数に異常がある病気であり、男性に発生する先天異常です。リスク因子や原因は様々ですが、性染色体の分離が不充分なことによって男性のX染色体が一つ以上多いことにより起きる性腺機能不全を主とした病態と言われています。
そもそも性染色体の異常とはどのような状態なのでしょうか。通常、男性は「XY」、 女性は「XX」の性染色体の組み合わせで性別が決定しています。しかしながらクラインフェルター症候群では、男性のX性染色体が1つ増える「XXY」や、2つ増える「XXXY」など、Xが少なくとも1つ以上多いことが特徴です。
クラインフェルター症候群において最も頻度の高い性染色体の核型は「XXY」であり、Xが一つ多い型です。「XXY」に比べて更に稀になりますが、クラインフェルター症候群の中でも「XXXY」や「XXXXY」などXの染色体が増えるほど、症状は強いとされています。
クラインフェルター症候群が起こるのは、男性が持つX染色体の数や構造に異常が原因となっています。しかし、病気の発症の原因であるX染色体に異常が起こるメカニズムについては明らかになっていません。
おなかの赤ちゃんが元気に生まれてくるには、両親から正しい数の染色体を受け継ぐ必要があります。人間の染色体は、44本の常染色体と2本の染色体があり、合計46本で構成されています。
46本の染色体の内訳は、以下のとおりです。
染色体が本来の数よりも多かったり少なかったりすると、受精卵の正常な発生が進みません。特に常染色体の数が多い場合では、受精卵後に胚(赤ちゃんの元)の分化が進まずに、そのまま死に至るので流産となります。
クラインフェルター症候群では、X染色体数が1つ以上で多いことで起こります。染色体の数が増えると、細胞分裂の際に起こる遺伝子のコピー数が増えるため、さまざまな症状の原因になります。
クラインフェルター症候群をはじめ、染色体の数の異常が起こる原因ははっきりしていません。一方で、染色体数異常を引き起こしやすい要因には、複数のものがあります。
多くの染色体数の異常に共通するように、高年齢の母親の妊娠はクラインフェルター症候群との関連があります。京都大学の研究では、以下のことが報告されました。
特に、35歳以上の妊婦さんでは、クラインフェルター症候群の赤ちゃんが生まれるリスクが高まることが分かりました。
このように、母親の年齢が高くなると、クラインフェルター症候群の要因となることが考えられます。
クラインフェルター症候群の要因は、女性の高齢出産だけでなく父親の年齢も関連があります。同じく京都大学の研究では、以下について報告されました。
上記のように、クラインフェルター症候群では、母親だけでなく高齢の父親のリスクになることが分かります。
おなかの赤ちゃんの性別は、性染色体が「XY」の組み合わせなら男の子、「XX」の組み合わせなら女の子になります。一方、クラインフェルター症候群では、「XXY」のように、X染色体が1つ以上ある状態になります。
そのため、クラインフェルター症候群の原因は、母親にあると考える人もいるかもしれません。しかし実際には、クラインフェルター症候群の原因になる余分なX染色体は母親由来か父親由来の可能性があります。
通常、染色体は父親と母親の両方から受け継ぐため、2対になっています。46本の染色体はそれぞれ対になっているので、23本の対になっています。
赤ちゃんの元となる受精卵は、精子と卵子が合体によって作られます。精子と卵子に限っては、合体後に2対になる必要があるため、染色体が対になっていません。
精子や卵子など生殖細胞を作る際には、染色体数を減らすための「減数分裂」がおこなわれます。そのため、性染色体は分裂により、男性の精子はX染色体かY染色体になり、女性の卵子はX染色体になります。
これまで見てきたように、父親または母親が高年齢であると、減数分裂にエラーが生じるため、精子がXとYの両方の性染色体を持つ「XY」や、卵子が2つ以上のX染色体を持つ「XX」となります。
これらの染色体数の異常がある精子と卵子が合体することで、受精卵に「XXY」や「XXXY」となるクラインフェルター症候群が生じるのです。

ここでは、改めてクラインフェルター症候群による身体的な特徴をみていきます。
| 男性性機能低下症 | 男性不妊症を引き起こす原因になる |
| 精巣発育不全 | 精巣が十分に発達せず、睾丸が十分に発達しない |
| テストテロンの分泌低下 | 健康な男性に比べて、男性ホルモンであるテストテロンの分泌が少なくなる |
| 女性ホルモンの分泌増加 | 余分にあるX染色体により、通常の男性よりも女性ホルモンの分泌レベルが高くなる。 |
| 第二次性徴がはっきり発現しない | テストテロンの分泌が低下するため、第二次性徴による男性らしさの発現が弱い傾向がある |
| 女性化乳房 | 女性ホルモンの分泌レベルが高くなることで、乳房が女性のように膨らむ |
| 発毛の女性化 | ヒゲやワキ毛が薄く生える |
| 男性不妊症 | 精巣が十分に発育しないため、精子が作られなかったり、数が少なかったりする |
| 高身長 | 高身長に合わせて、手足が長くやせ型の体型になりやすい |
またクラインフェルター症候群では、次のような精神的な症状がみられることがあります。
クラインフェルター症候群の原因となる性染色体「XXY」「XXXY」を持っていても、生まれてすぐ気づくとは限りません。クラインフェルター症候群の赤ちゃんは、健康な赤ちゃんと外見に大きな差がないためです。
クラインフェルター症候群についてご存知なくても、両親が子どもを受診させるきっかけとなるのが思春期です。クラインフェルター症候群の男の子は、思春期に胸が女性のように膨らんだり、陰茎や陰嚢が十分発達しなかったりなどの症状がみられます。
クラインフェルター症候群は、ホルモン補充療法によりテストテロンを補うことで、健康な男の子のように男性らしい体つきを目指すことができます。
一方、クラインフェルター症候群の子どもの中には、特有の症状が目立たずに、結婚後の不妊で医療機関を受診するケースもあります。
妊婦さんの中には、おなかの赤ちゃんがクラインフェルター症候群かどうか気になっている人もいるかもしれません。特に、父親か母親、または両親が高齢であると、クラインフェルター症候群のリスクが高くなります。
妊娠中におなかの赤ちゃんがクラインフェルター症候群かどうかを調べる検査に、NIPT(新型出生前診断)があります。NIPT(新型出生前診断)は、妊婦さんの血液中に含まれている、おなかの赤ちゃんのDNAの断片を解析する検査です。検査自体は採血だけで終わるので、妊娠中の体に大きな負担がかかりません。
大学病院等のNIPT(新型出生前診断)は調べられる病気が3つに限定されているため、クラインフェルター症候群について調べることはできません。
DNA先端医療株式会社では、世界基準のNIPTの検査項目を調べられますので、クラインフェルター症候群もお調べすることができます。
妊娠中におなかの赤ちゃんがクラインフェルター症候群かどうかを知ることで、自分の子どもに計画的に治療を受けさせることが可能です。

クラインフェルター症候群では、どのような合併症が発生するのでしょうか。具体的な病名を、理由と共にご説明します。
女性がかかるイメージの多い乳がんですが、頻度は少ないものの男性にも発生します。クラインフェルター症候群では男性ホルモンの生産が少ないことから、一般男性と比べ、かかりやすさは20-50倍と言われています。
男性ホルモンと血糖値に関連があることはご存じでしょうか。男性ホルモンの生産量が少ないクラインフェルター症候群では、血糖値のコントロールが難しいことがあり、結果的に肥満や糖尿病といった合併症に繋がります。
こちらも高齢の女性に多いイメージの骨粗鬆症ですが、骨密度は女性ホルモンの一つである「エストロゲン」が重要であり、特に閉経後の女性はエストロゲンが減ることから、骨粗鬆症になりやすいと言われています。
男性の場合、男性ホルモンの一つであるテストテロンを原料にエストロゲンは作られますが、クラインフェルター症候群では、エストロゲンの量も少なくなり、結果的に骨密度の低下から骨粗鬆症に繋がります。
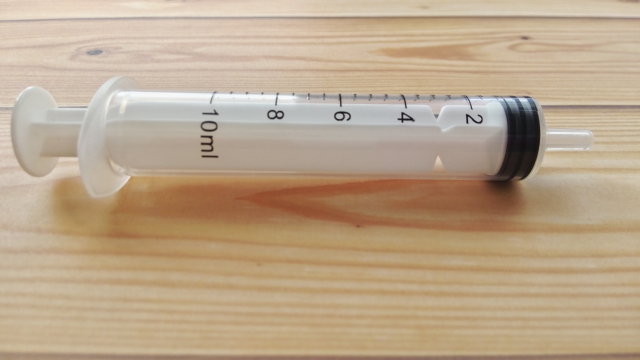
気クラインフェルター症候群を完治させる根本的な治療は存在せず、あくまで対処療法となります。以下それぞれの症状にあった対処療法について説明します。
代表的な治療がホルモン補充療法です。これは、男性ホルモンの生産量が少ないクラインフェルター症候群に対し、男性ホルモンを継続的に補充する療法になります。具体的には2-4週間に1度程度、注射で男性ホルモンを投与します。
男性ホルモンが投与されることから、筋肉量が増え、男性らしい体つきになる、骨密度が増えるといった効果があります。また継続的にホルモン補充療法を行うことは、将来的な肥満、糖尿病のリスクが軽減できるといった効果にもつながります。
程度や個人差はありますが、知能がやや低い、また学習障害、言語障害といった特徴がみられる場合は、療育(発達支援)を行います。クラインフェルター症候群はとりわけ言語能力に遅れがみられることがあります。
幼少期よりクラインフェルター症候群の診断がついた場合、学校や社会での生活に困らないよう、早い段階で継続的に専門家の療育(発達支援)を受けることができます。
精子の数が少ない乏精子症の場合、体外受精、顕微授精を行います。精子が確認できない場合、顕微鏡下精巣内精子回収術で精子を採取し、顕微授精に使用します。
クラインフェルター症候群は、20年程前までは治療困難な無精子症であり、妊娠は難しいと言われていました。しかしながら精巣機能の理解と治療、研究が進み、体外受精、顕微授精により子どもを持つことのできる割合は近年高まっています。

クラインフェルター症候群とは、性染色体の数に異常がある病気であり、約660人に1人の割合で男性に発生する先天異常です。
性染色体の分離が不充分であることが原因とされており、思春期以降に、いわゆる男性的な体つきが見られないことが身体的特徴です。その他、知的障害・発達障害・言語障害といった特徴も見られることがあります。
代表的な治療にはホルモン補充療法があり、男性ホルモンの継続的な投与を行います。
生殖機能について、精子が見られない、もしくは少ない場合、体外受精、顕微授精、微鏡下精巣内精子回収術での不妊症の治療を行うことで、子どもを持つことのできる割合は近年高まっています。
*キーワード:クラインフェルター症候群
【引用文献】
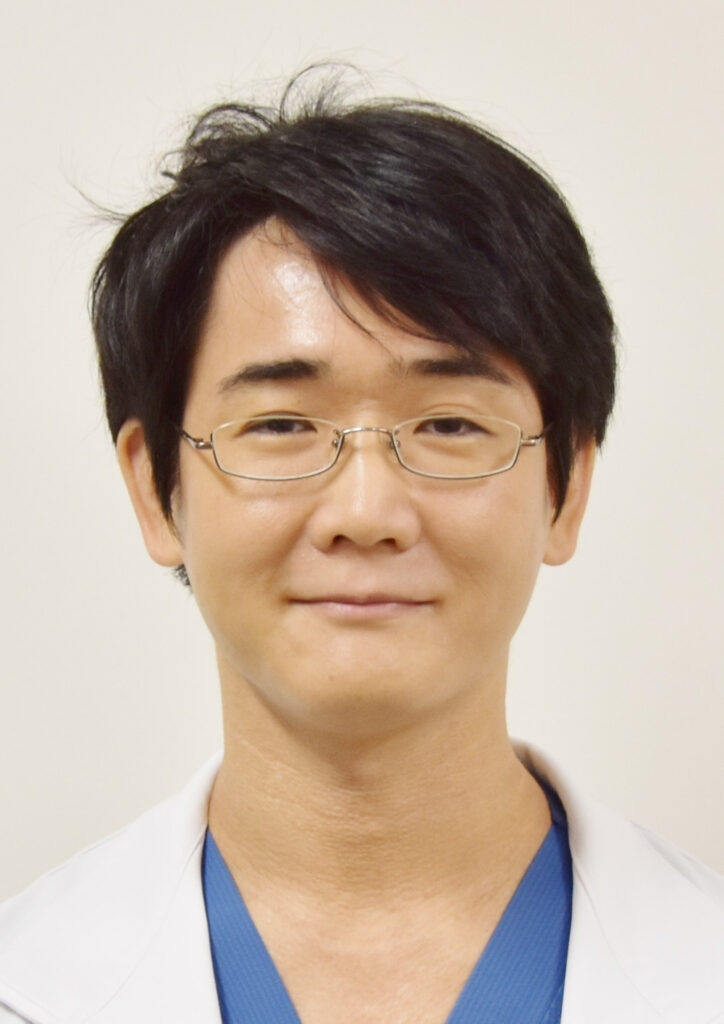
足立明彦先生
首都圏のセンター病院や徳洲会での勤務経験も持つ赤十字病院副部長・大学病院非常勤講師。ゲノム解析など遺伝子関連研究を行う医学者としても活動中。
取得資格:薬剤師、医師、博士(医学)、複数分野の専門医・指導医。
ABOUT ME