新生児期の子育ては、喜びと不安が入り混じります。「赤ちゃんの睡眠時間が長すぎるのではないか」と、心配になることもあるでしょう。
新生児の睡眠時間は個人差が大きくなりますが、1日16〜20時間程度が一般的です。寝すぎているように感じても、ほとんどが正常な範囲内のため、心配いりません。
この記事では、新生児の適切な睡眠時間や寝すぎる理由、安全な起こし方について解説します。記事を読めば、赤ちゃんの睡眠について正しい知識を得られ、安心して子育てに取り組みやすくなります。
新生児の睡眠時間の目安

赤ちゃんの睡眠時間は、月齢によって変化します。生後0~1ヶ月の新生児期は1日の大半を眠って過ごします。1日の睡眠時間は16~20時間程度で、昼夜の区別がありません。授乳のたびに起床するため、睡眠サイクルも短いのが特徴です。睡眠中の体温調節機能が未発達なため、快適な睡眠環境を整えてください。
生後1~2ヶ月になると3~4時間おきの授乳が必要です。夜間の睡眠時間が少し長くなり、環境音に反応しやすくなります。寝返りや首のすわりなどの発達が進むにつれ、睡眠中の体動も増えます。生後3ヶ月以降になると、睡眠時間は14〜17時間程度になり、昼夜の区別がついてきます。
夜間の睡眠時間が長くなり、昼寝の回数が減って1回あたりの睡眠時間が長くなります。夜10時頃~朝6時頃まで連続して眠る場合もあります。いずれの時期も、赤ちゃんによって個人差があるため、よく観察しましょう。
新生児が寝すぎる理由

新生児が寝すぎる主な理由は、下記のとおりです。
- 昼夜の区別がないため
- 成長ホルモンが分泌されるため
- 体力があまりないため
- 健康に問題があるため
昼夜の区別がないため
新生児は昼夜の区別がつかないため、24時間いつでも眠ります。理由は、赤ちゃんの体内時計がまだ発達していないためです。光や音などの外部刺激に対する反応が鈍く、睡眠サイクルが不規則です。赤ちゃんは生後2〜3ヶ月頃になると、徐々に昼夜のリズムができます。成長とともに体内時計が発達してくるためです。
新生児期は昼夜問わず眠るため、夜間の授乳や世話が必要です。赤ちゃんの成長過程では自然な流れのため、基本的に気にする必要はありません。長時間寝ていて心配な場合は、体重の増え方や授乳回数などをチェックしましょう。心配な点があれば、必要に応じて小児科医に相談してみてください。
赤ちゃんの健康と成長を見守りながら、適切にケアしましょう。
成長ホルモンが分泌されるため
新生児は、成長と発達のために睡眠中に成長ホルモンの分泌が活発になります。新生児期は、体のさまざまな部分が急速に発達します。成長ホルモンの効果は、下記のとおりです。
- 骨や筋肉の成長を促進する
- 脳を発達させる
- 免疫系を強化する
- 体重を増加する
成長ホルモンは体の組織を修復したり、新しく作り直したりする働きがあります。十分な睡眠は、赤ちゃんの成長と発達のために欠かせません。
体力があまりないため
新生児が長い時間眠る理由は、体力があまりないためです。体や脳の成長や発達に多くのエネルギーを使用していますが、体が小さく、長時間の活動ができません。睡眠は、新生児にとって体力回復のために不可欠な時間です。短時間で疲れてしまう新生児は、睡眠によって体力を補充しています。
健康に問題があるため

新生児の寝すぎには、健康上の問題が隠れている可能性があります。下記の問題が考えられるため、注意しましょう。
- 脱水
- 低体温
- 感染症
- 代謝異常
- 先天性の疾患
- 重症の黄疸
- 低血糖
- 呼吸器系の問題
- 栄養不足
- 脳の発達の問題
新生児の健康や発達に影響を与えるため、早期発見と適切な対応が重要です。脱水は体重減少や尿量の減少、皮膚の乾燥などが症状として現れます。低体温の場合、体が冷たく感じられたり、活気がなくなったりします。当てはまる症状があれば、小児科医に相談して適切な治療を受けましょう。
新生児が寝すぎるときのチェックリスト

基本的に新生児は寝すぎても心配ありません。しかし、健康状態に問題がないか、下記を参考にチェックしてみましょう。
- 体重の増え方
- 授乳回数
- 黄疸の症状
体重の増え方
新生児の体重があまり増えないときは、健康状態の問題が潜んでいる可能性があります。標準的な体重増加のペースに達していない場合は、注意が必要です。1日の体重の増加量をチェックし、停滞や減少していないか確認しましょう。
体重の増加が不十分な場合、赤ちゃんの皮膚のハリや弾力が低下したり、おむつの尿量が減少したりする場合があります。授乳後も体重が増えておらず、体重増加のグラフが標準曲線から大幅に外れていれば、要注意です。症状が見られるときは、早めに小児科医に相談してください。適切に対応すれば、赤ちゃんの健康を守りやすくなります。
授乳回数

授乳回数が少ないと、新生児の健康状態に影響を与えます。1日の授乳回数が6回未満で、授乳間隔が3~4時間以上の場合は注意が必要です。少ない授乳回数だと、栄養不足や脱水のリスクが高まります。母乳で育てている人は、乳房の張りが強くなる可能性もあります。
乳房の張りは、赤ちゃんが十分に母乳を飲んでいないことを示すサインです。授乳回数が少ないと感じたときは、必要に応じて小児科医に相談しましょう。
黄疸の症状
黄疸の症状には注意が必要です。黄疸は体内のビリルビンが増えて起こります。黄疸の主な症状は、下記のとおりです。
- 皮膚や目の白目が黄色くなる
- 尿の色が濃くなる
- 便の色が薄くなる
- 元気がなくなる
- 哺乳力が低下する
- 体重増加が鈍化する
- 発熱する
- 嘔吐や下痢がある
皮膚の変化は額から始まり、徐々に体全体に広がります。黄疸の症状があれば、すぐに医師へ相談してください。早期に発見して適切に治療すると、多くの場合は問題なく回復できます。赤ちゃんの健康を守るため、定期的に健康をチェックしましょう。
寝すぎる新生児を安全に起こす方法

寝ている新生児の安全な起こし方は、下記のとおりです。
- 体を優しくマッサージする
- おむつ替えで刺激を与える
- 部屋の明かりを調整する
体を優しくマッサージする
新生児を安全に起こすためには、体を優しくマッサージしましょう。赤ちゃんの体に触れると、穏やかな刺激を与えられます。手のひらで優しく顔や体をなで、腕や脚を軽くさすります。背中を円を描くようにマッサージして、足の裏を優しくなでましょう。マッサージはゆっくりと行います。
赤ちゃんの反応を見ながら、力の入れ具合を調整してください。力を入れすぎないように注意が必要です。赤ちゃんの体温を下げすぎないよう、温かい手で触れましょう。マッサージは赤ちゃんを優しく目覚めさせるだけでなく、スキンシップを通じて親子の絆を深める効果もあります。
おむつ替えで刺激を与える

優しく話しかけながらおむつを替えると、赤ちゃんの覚醒を促せます。体を拭くときに軽くマッサージし、新しいおむつをつける前に足を軽く動かしましょう。赤ちゃんの顔を覗き込んで目を合わせるのもおすすめです。おむつ替えでスキンシップを取ると、赤ちゃんの感覚を刺激し、脳の活動を活発にします。
歌を歌ったり、明るい場所でおむつを替えたりするのも効果的です。ただし、刺激を与えすぎないよう注意が必要です。赤ちゃんの様子を見ながら、優しく行いましょう。おむつ替え後に抱っこして体を起こすなど、赤ちゃんの状態に合わせて対応してください。
部屋の明かりを調整する
部屋を明るくすると、新生児を起こすのに効果的です。カーテンを開けて自然光を取り入れて、赤ちゃんの体内時計を整えましょう。ただし、直射日光が赤ちゃんの顔に当たらないよう注意してください。突然明るくなると赤ちゃんが驚くため、少しずつ明るくするなど調整しましょう。
調光機能付きの照明器具を使用すると、細かな調整ができるため、おすすめです。間接照明を使用して柔らかな光の環境を作るのも効果的です。赤ちゃんの目の高さを考慮して照明の位置を調整し、目に光が当たらないよう配慮してください。朝は明るく、夜は暗めにするなど、時間帯に応じて明るさを調整します。
目覚まし時計型のライトを使用するのもおすすめです。授乳や世話をするときは最小限の明るさにとどめ、赤ちゃんの快適な睡眠環境を維持しましょう。
新生児の寝すぎが気になるときの対処法

新生児が寝すぎて気になるときの対処法は、下記のとおりです。
- 睡眠リズムを整える
- 定期的に健康チェックする
- 小児科医に相談する
睡眠リズムを整える
新生児の成長と発達のためには、睡眠のリズムを整えましょう。睡眠リズムが整うと、赤ちゃんの体内時計も整い、夜間の睡眠時間が長くなります。就寝前のルーティンを決めるのもおすすめです。入浴や軽いマッサージで、赤ちゃんをリラックスさせてください。静かな睡眠環境を整えるのも大切です。
夜間の授乳や世話は最小限に抑え、赤ちゃんの生体リズムに合わせて徐々に調整しましょう。赤ちゃんの睡眠パターンは個人差があるため、焦らず根気強い取り組みが大切です。
定期的に健康チェックする

定期的な健康チェックは、異常を早期に発見するために重要です。赤ちゃんの体調の変化がわかると、適切な対応ができます。下記の項目を定期的にチェックしましょう。
- 体重や体温
- 皮膚の色や状態
- 排泄物の量や色
- 哺乳力
- 呼吸の様子や音
- 泣き方や機嫌の変化
日常的にチェックすると、赤ちゃんの健康状態の変化を把握できます。専門家による定期的な健康診断も重要です。予防接種のスケジュールを管理し、発育・発達の確認のための受診も忘れずに行いましょう。
小児科医に相談する
新生児が寝すぎて気になる場合は、小児科医に相談しましょう。医師の意見を聞くと、健康上の問題の有無がわかり、適切に対応できます。小児科医に相談するときは、下記の点を伝えてください。
- 睡眠パターン
- 生活リズム
- 体重増加や発達の状況
- 気になる症状や行動
- 授乳回数や量
情報量が多ければ、医師はより正確な判断ができます。家族の不安や心配事も率直に話しましょう。医師の指示に従い、必要に応じて検査を受けてください。定期的に受診すると、今後の対応方法や注意点についてアドバイスをもらえます。緊急時の連絡先や対処法も確認してください。
新生児の健康を守るためには、気になる点を小児科医へ相談しましょう。
新生児が寝すぎるときによくある質問

新生児が寝すぎるときによくある質問は、下記のとおりです。
- 新生児は寝すぎると病気になる?
- 寝ている間に授乳する?
新生児は寝すぎると病気になる?
新生児が寝すぎると病気になる可能性は低く、むしろ十分な睡眠は成長に不可欠です。しかし、過度の睡眠が続く場合は注意してください。睡眠パターンが通常と異なるときは、健康上の問題が発生している可能性があります。授乳回数が減少したり、体重があまり増えなくなったりしたら注意しましょう。
黄疸や脱水などの症状があれば、すぐに小児科医に相談してください。睡眠中の赤ちゃんの様子をチェックするのも大切です。呼吸や体温を確認し、異常がないか観察しましょう。病気の兆候がなければ、十分な睡眠が大切です。
寝ている間に授乳する?

赤ちゃんの健康と成長のために、生後3ヶ月までは3〜4時間おきの授乳が必要です。夜間の授乳は母乳の分泌を促進し、赤ちゃんの体重増加につながります。母子の絆を深めるためにも大切な時間です。寝ている赤ちゃんを起こさずに授乳ができるため、睡眠リズムを乱さずに必要な栄養を与えられます。
夜間の授乳は、赤ちゃんの快適な睡眠につながり、空腹で目覚めるのを防ぎます。ただし、赤ちゃんの成長に合わせ、回数を徐々に減らしていきましょう。赤ちゃん一人ひとりの状況に合わせて、授乳のタイミングを調整していくことをおすすめします。
まとめ
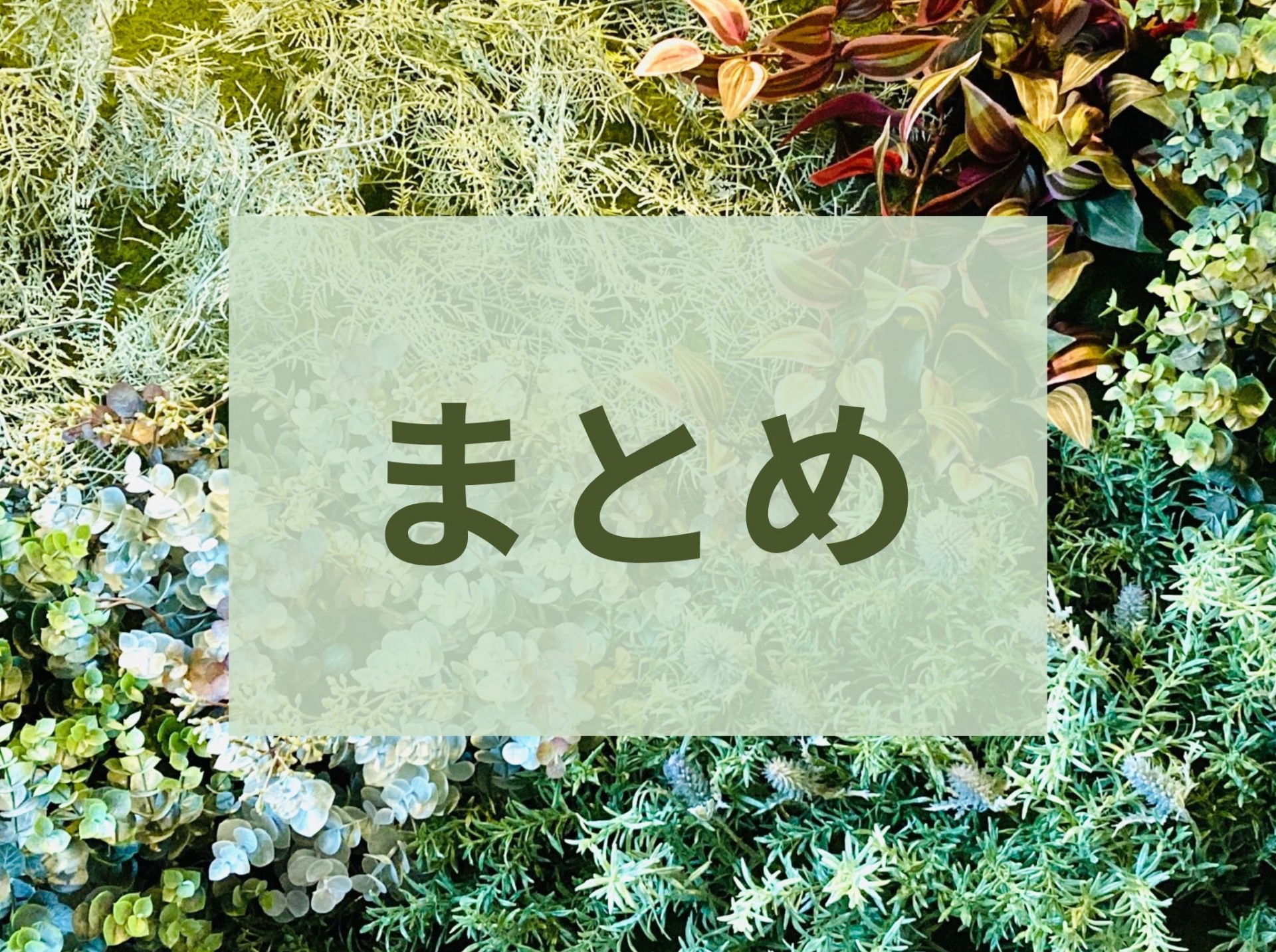
新生児の睡眠について多くの親が不安を感じますが、基本的に寝すぎを心配する必要はありません。新生児の睡眠時間は月齢によって変化します。睡眠時間が長い理由は、生理的な要因です。一方で、体重が増加しなかったり、授乳回数が減少したりする場合は注意しましょう。
寝ている新生児を安全に起こす方法として、マッサージやおむつ替えで刺激を与えるのが効果的です。寝すぎが気になるときは、小児科医に相談しましょう。病気の心配はほとんどありませんが、定期的な授乳は欠かせません。新生児の睡眠について理解し、安心して育児に取り組みましょう。










